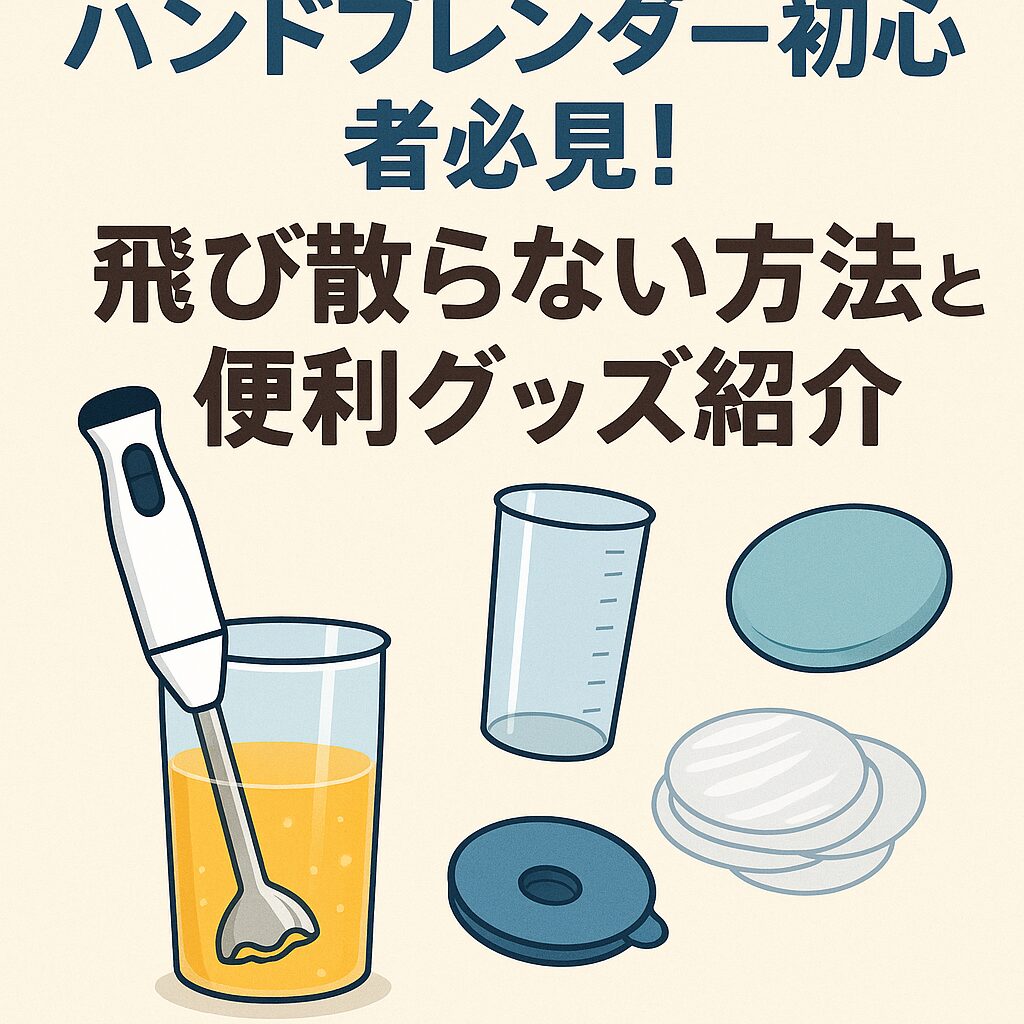「スープやスムージーを作るたびにキッチンがビチャビチャ…」「エプロンまで汚れてイライラ!」
そんな経験、ありませんか?
ハンドブレンダーは便利な調理アイテムですが、使い方を少し間違えると、食材が飛び散って大惨事に。
この記事では、「飛び散らないハンドブレンダーの使い方」や便利グッズ、プロのテクニックまで徹底解説します。
もう汚れとはサヨナラ!今日からあなたもブレンダー名人に!
ハンドブレンダーの飛び散らない方法
正しい容器の深さと形状を選ぼう
ハンドブレンダーで食材を混ぜるとき、一番大切なのは容器選びです。
深さが足りないボウルや広がったお皿では、回転時に食材が飛び散りやすくなります。
理想は「縦に深く、口が狭い」容器です。
こうした容器なら、ブレンダーの回転で生まれる渦が食材を下に引き込むので、周囲に飛び散りにくくなります。
市販のブレンダーに付属している専用カップは、この構造を考えて作られていることが多いので、できるだけそれを使うのがベストです。
もしそれがない場合は、500ml以上の容量がある深めの計量カップや保存容器が代用になります。
また、容器の素材にも注目。
ガラス製よりもプラスチック製のほうが軽くて扱いやすく、万一落としても割れにくいという利点があります。
ただし耐熱性の有無はしっかり確認しておきましょう。
特に温かいスープなどを作るときには、耐熱容器を選ばないと危険です。
調理中に飛び散るとキッチンが汚れてしまい、掃除の手間も増えます。
だからこそ最初の一手、容器選びを正しくするだけで、その後の工程がぐんと楽になります。
ブレンダーの先端を沈めてからONに
ハンドブレンダーを使う際、つい空中でスイッチを入れてしまう人がいますが、これは絶対にNG。
ブレンダーの刃が空回りして空気を巻き込み、一気に食材が弾け飛ぶ原因になります。
正しい順番は「先にブレンダーの先端を容器の底まで沈めてから、スイッチを入れる」こと。
こうすることで、ブレンダーの回転が直接食材に伝わり、飛び散りにくくなります。ポイントは「底に密着させる」ことです。
さらに、ONにしたあともすぐに動かさないでください。2〜3秒はそのまま静止して、材料がしっかりと回転に巻き込まれるのを待ちます。
その後、ゆっくりと上下に動かして混ぜていきましょう。
このステップを守るだけでも、飛び散りのリスクは大幅に減ります。
「使い方次第でここまで変わるのか!」と驚くはずです。
材料を入れすぎないのがコツ
容器に食材をたっぷり入れてしまうと、回転中に行き場を失った材料が上に押し上げられてしまい、飛び散る原因になります。
特にスープやスムージーのような液体が多いものは、容器の半分〜2/3までを目安にしましょう。
材料が多すぎると、ブレンダーの刃にかかる負荷も増えてモーターに負担がかかりますし、故障の原因にもなります。
安全に、そして美しく調理するためには「少しずつ」が鉄則です。
また、材料を入れる順番も工夫しましょう。
液体が多い場合は、固形物を先に入れて、そのあとで液体を注ぐと、撹拌がスムーズになります。
液体が先に入っていると、跳ね返りやすくなるので注意が必要です。
一度で済ませようとせずに、量を分けて数回に分けてブレンドすると、キッチンを汚さずに済みますよ。
スイッチの押し方と速度の調整法
ハンドブレンダーのスイッチは、多くのモデルで強弱が選べるようになっています。
最初から「強」で動かすと、パワーがありすぎて材料が飛び出してしまうことがあります。
まずは「弱」モードでスタートし、材料が馴染んできたところで「中」や「強」に切り替えると、安定した攪拌ができます。
また、スイッチの押し方も重要です。
いきなり「ガチッ」と力強く押すと、ブレンダーがガクッと動いてしまい、思わぬ方向に材料が飛び散ることも。
優しく押して、回転が滑らかに始まるよう意識してみてください。
長押しし続けるのではなく、数秒押して少し止める「間をあける使い方」も有効です。
この方法だと材料が一気に撹拌されすぎず、飛び散りを防げるだけでなく、ムラなく仕上がるという利点もあります。
どんな料理でも「急がば回れ」。
丁寧な操作がキレイな仕上がりのカギです。
作業中の手の角度と位置に注意
作業中、意外と見落とされがちなのが「手の角度」です。
ブレンダーを斜めに構えると、刃の回転が食材を上に巻き上げやすくなります。
そうすると、せっかくの容器が深くても意味がありません。
必ず「まっすぐ垂直に」ブレンダーを差し込むことが大切です。
また、作業する手の位置が高すぎたり、ブレンダーの持ち手がブレていると、不安定になり、飛び散る可能性が増えます。
両手でしっかりと容器とブレンダーを固定し、腕や肘を安定させると作業が楽になります。
調理台の高さにも注意しましょう。
高すぎたり低すぎたりすると、角度がズレてしまいやすいです。
自分の肘が少し曲がるくらいの高さで作業できるよう調整するとベストポジションになります。
ちょっとした姿勢の工夫でも、飛び散りはしっかり防げます。
実際に意識してみると、「なんで今まで気づかなかったんだろう」と感じるほど、違いを実感できますよ。
飛び散る原因とその仕組みを知ろう
ブレンダーの回転の仕組みとは?
ハンドブレンダーの飛び散り問題を理解するには、まずその構造を知ることが大切です。
ブレンダーは先端に小さな刃がついており、その刃が高速回転することで食材を細かく砕いたり混ぜたりしています。
この回転によって発生するのが「渦流(うず)」です。
この渦流がしっかり容器内に収まっていれば問題ないのですが、容器が浅かったり、ブレンダーの位置がズレていたりすると、食材が渦に乗って上方向へ飛び出すのです。
特に液体が多いと水しぶきのように飛び散ることも。
つまり、ハンドブレンダーは単なる「かき混ぜる道具」ではなく、「回転による圧力と流れで素材を移動させる道具」なのです。
この流れをうまくコントロールできれば、飛び散りもかなり減らせます。
特に高速回転する「ターボモード」などを使う場合は、この渦の力が強くなるため、より深い容器やふたの工夫が必要です。
なぜ浅い容器だと飛び散る?
浅い容器は飛び散りの元凶です。
なぜなら、ハンドブレンダーが発生させる強い渦流が逃げ場を失い、上へと跳ね返ってしまうからです。
これは水風船を思いきり握ったときに水が四方八方に飛ぶのと同じ原理です。
また、浅い容器だとブレンダーの刃が外気に近くなり、空気を巻き込みやすくなります。
これにより「泡立ちすぎる」「食材が飛び跳ねる」といった現象も起きやすくなります。
さらに、容器が浅いとブレンダーの角度をうまく調整できず、斜めに使ってしまいやすいのも問題です。
刃が容器の底にしっかり当たらないことで、余計な飛び散りが生まれることもあります。
目安として、最低でもブレンダーの長さの2倍以上の深さがある容器を選ぶと安心です。
食材によって飛びやすさが違う?
食材の種類によっても飛び散りやすさは異なります。
とくに液体と固形物が混ざった状態のときに飛び散りやすい傾向があります。
たとえば、以下のような食材は要注意です。
| 食材 | 飛び散りやすさ | 理由 |
|---|---|---|
| ミルク系スープ | 高 | 液体が軽くて飛びやすい |
| トマト | 高 | 水分が多く破裂しやすい |
| 果物(バナナ以外) | 中 | 柔らかいが水気が多い |
| 芋類のペースト | 低 | 粘度が高く安定している |
| 氷入りスムージー | 高 | 固形が飛び出す力を持つ |
特に「氷」や「皮つき野菜」などは回転時に跳ね返ることもあるため、カットの仕方やブレンダーの押し込み方に工夫が必要です。
飛び散りやすい使い方の典型例
飛び散りやすい使い方にはいくつかのパターンがあります。
以下にその典型例を紹介します。
- 空中でスイッチON
→ 食材がない状態で回転すると空気を巻き込み、一気に飛び跳ねます。 - 容器いっぱいに材料を入れる
→ 容器に余裕がないと、渦で持ち上がった食材がすぐにあふれます。 - 途中でブレンダーを引き抜く
→ 作動中に引き抜くと、回転中の刃が外気に触れ、食材が噴き出します。 - 斜めに持って使う
→ 食材の撹拌が偏り、飛び散りやすくなります。 - 液体から固体をすくいあげる動き
→ 材料の一部が刃に当たり、勢いよく飛ぶことがあります。
これらはすべて「ブレンダーの使い方」に関わるものなので、ちょっとした意識で大きく改善できます。
「音」でわかる危険サインとは?
意外に知られていないのが、「音」で飛び散りの前兆がわかるということ。
通常、ブレンダーが安定して撹拌しているときの音は「ウィーン」という一定の低めの音です。
ところが、刃が空回りしている場合や、材料が暴れているときは「バタバタ」「シュワシュワ」といった高めで不安定な音がします。
これが「飛び散り注意」の合図です。
また、材料が刃にうまく絡んでいないときも音が軽くなります。
この場合は位置を調整して、刃がしっかり食材に当たるようにすると音が落ち着き、飛び散りも収まります。
キッチンで音に敏感になることも、安全で効率の良い調理には欠かせません。
使い方のコツをマスターしよう
下から上へ動かすのが基本
ハンドブレンダーの動かし方にも、飛び散りにくい「基本の流れ」があります。
それは「下から上へ、そしてまた下へ」という上下の動きです。
まず、ブレンダーを容器の底に密着させ、スイッチを入れたままゆっくり上に持ち上げていきます。
そして再びゆっくりと下げていきます。
この動作を繰り返すことで、材料が均一に混ざりながらも、飛び散りを最小限に抑えることができます。
この上下運動をリズミカルに行うことで、刃の動きが一定の食材を無駄なくとらえ、撹拌にムラが出にくくなります。
また、材料が浮かび上がってもすぐに沈めることができ、飛び跳ねを防げるのです。
よくあるNG例は「左右に振る」「円を描くように動かす」といったやり方。
これは回転の流れを乱してしまい、思わぬ方向に材料が飛び出す原因になります。
正しい動かし方を体に覚えさせることで、どんな料理にも応用できる安定した使い方が身につきます。
斜めに差し込むとNGな理由
「斜めに差し込むと作業しやすいのでは?」と思ってしまうかもしれませんが、これは実は飛び散りの大きな原因になります。
ハンドブレンダーは、刃が均一に回転してこそ最大の効果を発揮します。
斜めに差し込むと、一部の刃にだけ負荷がかかり、回転のバランスが崩れてしまいます。
その結果、材料が斜め方向に勢いよく飛び出し、容器の外まで飛び散る可能性が高くなります。
さらに、斜めに押し込むことで、ブレンダーの軸にも負担がかかり、故障の原因にもなります。
常に「垂直に差し込む」ことを意識しましょう。
特に深さのある容器を使っていると、無意識に斜めに持ってしまうことがあるので要注意です。
もしブレンダーを持つ腕が疲れる場合は、容器を少し傾けるか、調理台の高さを調整することで、自然と垂直に保ちやすくなります。
液体と固形物の順番がポイント
材料を入れる順番にも工夫が必要です。
たとえばスムージーやスープなどを作る場合、先に固形物を入れてから液体を注ぐと、ブレンダーの刃にしっかり食材が触れて混ぜやすくなります。
逆に、液体を先に入れると、刃が空回りしてしまい、飛び散りやすくなります。
液体の上に軽い材料(たとえばほうれん草の葉など)が浮かんでいると、刃に巻き込まれて跳ね返る危険もあります。
理想的な順番は「固形物 → 液体 → ブレンダー」の順です。
液体が少なめのときは、途中で足していくようにすると、撹拌の状態を確認しながら作業できます。
この順序は飛び散り防止だけでなく、滑らかな仕上がりにもつながるので、特にスムージーやポタージュなど見た目も大事な料理では大きな差が出ます。
一度に混ぜずに小分けにする
ついつい一度に全部混ぜたくなってしまいますが、ハンドブレンダーでの調理では「少量ずつ小分けにして混ぜる」ことが成功のコツです。
材料が多すぎると、刃がうまく食材に届かず、ムラが出るだけでなく、飛び散るリスクも一気に高まります。
特にスープやフルーツミックスのような液体+固形のレシピでは、半分ずつ、または三分の一ずつに分けて混ぜるのが効果的です。
容器の容量が小さくても、数回に分ければ問題ありません。
また、混ぜ終わったら一度別の容器に移し替えて、次の分を混ぜるという手間を惜しまないことが、キッチンをきれいに保つためには重要です。
時短のつもりで一気に混ぜると、結局掃除に倍の時間がかかってしまうこともありますので、丁寧な手順を心がけましょう。
少量調理のときの注意点
少量の材料を混ぜる場合、ハンドブレンダーの刃がうまく材料に当たらず、空回りして飛び散ることがあります。
たとえばドレッシングや少量の離乳食などを作る際には、刃の高さと材料の高さが合っているかを確認することが大切です。
そんなときに便利なのが「小さめで深い容器」です。
食材が刃にしっかり接するようにすることで、安定して撹拌できます。
また、材料の量に合わせてブレンダーのスピードを調整することも忘れずに。
少ない材料には「弱」モードで、じっくりと混ぜていきましょう。
もし材料が本当に少ない場合は、スプーンであらかじめ潰しておくと、ブレンダーの効果が出やすくなり、飛び散りも防げます。
細かい工夫が、仕上がりと後片付けの手間に直結します。
おすすめアイテム&便利グッズ
飛び散らない専用ブレンダーカップ
ハンドブレンダーの使用時に最も頼りになるのが、専用設計のブレンダーカップです。
多くのブレンダーには初めから付属しており、そのサイズや形状は飛び散りを防ぐために最適化されています。
特に「縦長で底が狭く、口が広すぎない」デザインは、渦の力をうまく抑え、食材を容器内にとどめる効果があります。
また、目盛り付きのカップは分量を量りながら作業できて便利。
耐熱タイプであれば、スープなどをそのまま温め直すこともでき、洗い物の手間も減らせます。
もし付属のカップが使えなくなった場合でも、代替品として販売されている専用容器を購入する価値は十分にあります。
特にメーカー純正のものはサイズ感もピッタリで、安定感も抜群です。
「飛び散らない」を本気で目指すなら、まずこの専用カップの活用から始めてみましょう。
ラップやシリコン蓋の応用テク
飛び散り対策としておすすめなのが「ラップ」や「シリコン蓋」を使ったカバー技です。
やり方は簡単。深めの容器に材料を入れ、ブレンダーを差し込んだら、上からラップやシリコン蓋をかぶせるだけ。
刃が回転しても食材が上に飛び出さないので、周囲が汚れにくくなります。
ラップの場合は、真ん中にハンドブレンダーの棒が通るように小さな穴を開けて使います。
シリコン蓋なら、伸縮性があるのでしっかりフィットし、より安全に使えます。
耐熱タイプならスープや温かいソースにも使えるのが便利です。
これらの方法は特に「柔らかい果物」や「粘度のある液体」を使うときに効果的です。
短時間でサッと済ませたい朝のスムージー作りにもぴったり。
ちょっとした手間で飛び散りゼロを実現できる、賢いテクニックです。
飛び散り防止のカバーグッズ
最近は、ハンドブレンダー専用の「飛び散り防止カバー」も販売されています。
これは、カップの上に取り付けるプラスチックやシリコン製の蓋で、中央にブレンダーを通す穴があいています。
このような製品は、特に離乳食やドレッシングなど「少量を確実に撹拌したいとき」に重宝します。
サイズや形状がブレンダーの先端に合わせて設計されているため、装着も簡単で、洗うのもラクです。
1000円前後で購入できるものが多く、コストパフォーマンスも◎。
繰り返し使えるので、プラスチックごみの削減にもつながります。
また、子どもと一緒に料理をするときなど、安全面にも配慮したい場面で大活躍。
飛び散りを防ぐだけでなく、安心して作業できる環境も整います。
100均グッズでも代用可能?
実は、100円ショップに売っているキッチングッズでも、飛び散り対策は可能です。
たとえば、深型のプラコップや、ドレッシングボトルのような細長い容器を代用することで、かなり飛び散りを抑えることができます。
また、シリコン製のふたや、耐熱性のあるボウルカバーなども便利です。
中にはブレンダーを通せる穴があるタイプもあり、見た目以上に使い勝手が良いです。
「お皿の裏側をふた代わりにする」なんてアイデアもあります。
容器にお皿をかぶせて、そこにブレンダーを差し込めば、簡易カバーの完成。
完全な密閉はできませんが、短時間なら十分に効果があります。
手軽な材料でここまでできるのかと驚くほど、アイデア次第で飛び散り対策は可能です。
節約派の方にもおすすめの方法です。
人気メーカーの工夫された設計
最近のハンドブレンダーは、各メーカーが「飛び散りにくさ」を重視した設計を導入しています。
たとえば、刃の周囲をカバーするような特殊な形状のガードが付いていたり、回転時の渦を調整するための凹凸があったりします。
ブラウン、パナソニック、ティファールなどの有名メーカーでは、飛び散りを抑えるための実験を重ねて設計されており、実際に使ってみると「確かに汚れにくい」と実感できるものが多いです。
特に「アクティブブレード」や「スプラッシュコントロール」などの技術は、飛び散り防止だけでなく、食材の引き込み効率もアップさせており、時短にもつながります。
新しいブレンダーを検討している方は、こうした機能に注目して選ぶと、ストレスのない調理が実現できます。
飛び散りゼロを実現するための総まとめ
初心者でもすぐできる実践テク
「ブレンダーを使うとキッチンが汚れる」と敬遠していた方も、ちょっとしたコツを覚えれば飛び散りゼロも夢ではありません。
以下のような簡単な実践テクニックを取り入れることで、初心者でも安心して使えます。
- 容器は深めで狭口のものを選ぶ
→ 渦が暴れにくく、食材が逃げにくい。 - ブレンダーの先端を完全に沈めてからON
→ 空回りによる飛び跳ねを防止。 - 材料は容器の半分〜2/3程度に
→ 溢れる心配なしで安定撹拌。 - 「弱」モードからスタートする
→ 飛び跳ねずに滑らかに混ざる。 - 混ぜるときは垂直に、ゆっくり上下動作
→ 均一に混ざり、周囲も汚れにくい。
このように、ちょっとした工夫で飛び散りの悩みはグッと軽減します。
実際に使ってみると、「え、これだけで?」と驚くほど違いを感じるはずです。
プロの料理家が教える裏ワザ
料理研究家やプロのシェフたちも、日々の現場でブレンダーを使いこなしています。
彼らが口を揃えて言うのが「動かすのは刃じゃなくて材料」だということ。
つまり、ブレンダーはなるべく動かさず、容器や材料の位置を変えることで、食材が刃の中心に集まるようにするのがコツです。
また、食材をあらかじめ小さくカットしておくことも、飛び散り予防だけでなく、撹拌の効率もアップします。
さらに、プロはラップやお皿をカバーに使うことも日常的。
汚れを最小限にするための「段取り」がうまくできるようになると、料理全体のスピードも上がります。
プロのテクはすぐに真似できるものばかりなので、ぜひ取り入れてみてください。
ブレンダーの選び方にも注目
飛び散りにくさは、ブレンダー本体の性能にも関係しています。
たとえば、刃のカバー部分が深めになっているものや、回転時の渦を抑える設計のものは、それだけで飛び散りにくくなります。
また、スピード調整が細かくできる機種や、素材ごとのモード切り替えがあるものも便利です。
特に初心者の方には、オート機能付きのモデルがおすすめです。
必要以上のパワーで回転しないため、飛び散りを防ぐ効果が高いです。
本体の重さや持ちやすさも重要です。
長時間の使用で手が疲れて傾きがちになると、斜め使用によって飛び散る可能性が高まります。
手になじむグリップ形状の製品を選ぶことで、正しい姿勢をキープしやすくなります。
購入時には「飛び散り防止設計」や「スプラッシュガード付き」などの記載にも注目しましょう。
清掃の手間も減る使い方
飛び散りを防ぐことで、何より嬉しいのが「片付けが楽になる」ことです。
ブレンダー周りやキッチンの壁、衣服が汚れていなければ、作業後のストレスは大きく減ります。
さらに、容器を使い分けることで洗い物も少なく済ませることができます。
たとえば、調理から保存まで使える耐熱カップを活用すれば、ブレンダーで混ぜてそのまま冷蔵庫へイン。
また、ブレンダーの先端部分は取り外してすぐに水洗いできるモデルを選ぶと、毎回の清掃がわずか1分程度で済みます。
こびりつきが気になるときは、ぬるま湯と中性洗剤を入れて数秒回転させるだけで、内部の洗浄も完了します。
つまり、飛び散りを減らすことは「調理のスマート化」にもつながるのです。
まとめてわかる「飛び散り対策」チェックリスト
最後に、今まで紹介してきた内容を「チェックリスト形式」で整理してみましょう。
これさえ押さえれば、飛び散りトラブルとは無縁です。
| チェックポイント | 実践できてる? |
|---|---|
| 深さのある容器を使っているか? | ✅ / ❌ |
| ブレンダーを沈めてからONにしているか? | ✅ / ❌ |
| 材料を入れすぎていないか? | ✅ / ❌ |
| スピード調整を使いこなしているか? | ✅ / ❌ |
| 動かし方は上下で一定か? | ✅ / ❌ |
| ラップや蓋などで飛び散り対策をしているか? | ✅ / ❌ |
| ブレンダーの角度は常に垂直か? | ✅ / ❌ |
| 小分けして混ぜる工夫をしているか? | ✅ / ❌ |
この表をプリントアウトしてキッチンに貼っておくと、いつでも見返せて便利です。
飛び散りゼロの快適キッチン、ぜひ実現してみてください。
まとめ:もう飛び散らない!ハンドブレンダーはちょっとの工夫で劇的に変わる
ハンドブレンダーを使うときに悩まされがちな「飛び散り問題」。
でもその原因の多くは、実はちょっとした使い方の違いや道具選びにあります。
容器の深さや形状、スイッチの入れ方、ブレンダーの角度、材料の順番といったポイントをおさえれば、キッチンが汚れることも少なくなります。
さらに、100均グッズや専用アイテムを使えば、初心者でも簡単にプロのような調理が可能になります。
飛び散り対策は、仕上がりを美しくするだけでなく、後片付けの手間を減らし、料理そのものの楽しさもアップさせてくれます。
今回ご紹介したテクニックをぜひ実践して、毎日の料理をもっとスムーズで快適にしてみてください。